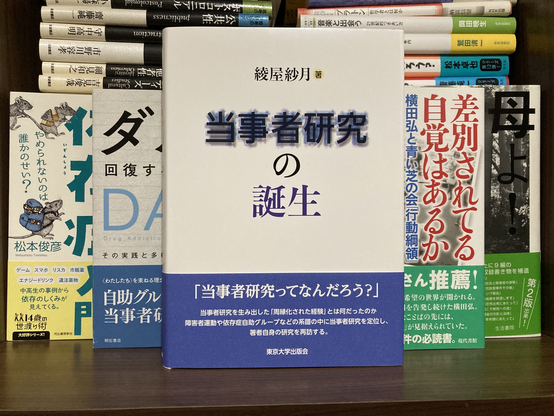#当事他者探究 #当事他者探Q
https://note.com/haveakiller/n/nd52e253623b6
当事他者探Qその9|当事他者論
「当事者」を「体験専門家」、「当事他者」を「経験好事者」としました。ここでまた再び「体験と経験」について考えてみます。 前回は、「体験」と「経験」とを区別し、「体験」はある出来事に直面することとして、「経験」は体験した出来事を他者と分かちあえることとしました。さらにこの両者は真っ直ぐには繋がっておらず、「実験」をその間に挟むのではないかと思います。つまり「体験」は「実験」を経て「経験」になる。ではそれは何の「実験」なのかといえば、その一つとして「追体験」とも呼べるようなものと考えています。 「追体験」と言ったとき、それは「未体験」の当事他者が、当事者の「体験」を「追体験」する
当事他者探Qその8|当事他者論
友人より横道誠さんが「当事者」を「経験専門家」としても捉えていると教えてもらい、ヒントになりそうなので考えてみましょう。考えるにあたって、「経験」と「専門家」とを分けたいと思います。 これまで「経験」を「体験」と区別してきました。「体験」はある出来事に直面することとして、「経験」は体験した出来事を他者と分かちあえるようにすることとすると、「当事者」を「体験」と、また当事他者を「経験」と結びつけて考えることができます。 山崎孝明さんも野口裕二さんの現代社会の見取り図を参照しながら、「体験に基づいた当事者」という言い方をしており、それに対立するものとして、「エビデンスに基づいた専門
#当事他者 #当事他者探究 #当事他者探Q #当事他者論
https://note.com/haveakiller/n/n7e8008c3ad45
当事他者探Qその7|当事他者論
当事者の体験を、当事他者と言語化して経験にすることを、ベンヤミンの言語論に沿って考えてみましょう。 ベンヤミンは「言語一般および人間の言語について」という論考において、言語は人間以外の事物にもあるけれども、それは音を持たない沈黙の言語だとしています。それに対して人間の言語すなわち言葉は、事物を認識して音声にすること、つまり事物を名づけることを本質としています。当事者の体験を経験へと言語化することは、事物の言語を人間の言葉で名づけることでもあります。 事物を名づけることは、「翻訳」とも呼べる営みであり、「翻訳者の課題」という論考にも引き継がれています。ベンヤミンは「翻訳者の課題
#当事他者論 #問事者 #当事他者 #当事他者探究 #当事他者探Q
https://note.com/haveakiller/n/n8b31f50a5613
当事他者探Qその5|非当事者研究
出来事の不確かさを受け止めて問いを開始する「問事者」には、二つの側面すなわち受動と能動の側面があります。まず一つには、出来事を受け止める、逆に言えば、出来事に問われる受動的側面があり、またもう一つには、出来事を問う能動的側面があります。 「問事者」は、まず出来事を受け止めて、次に問い始めるといった順序を辿るように思えますが、必ずしもそういうわけではなく、むしろ問い始めることで、出来事を受け止め自覚することができるようにも思います。この辺りは、世界に投げ出された存在が自己を開く、「被投的投企」とも関連しそうです。 話を戻すと、この「問事者」の受動と能動との側面はそれぞれ、「当事
当事他者探Qその4|非当事者研究
前回の「共同存在」について述べた際、「現存在と他者」を「当事者と当事他者」に置き換えました。それはいわば「現存在」は「当事者」であると言っているようなものです。しかしそれはあながち外れていないのではないかと思います。 「現存在」という言葉を、前回はとりあえず人間の意味で使いましたが、実際にそれが言わんとするのは、存在を問う人です。存在といっても、あまりにも漠然としています。存在を問う人にとってまず存在するのは、問う人自身すなわち「この私」であり、「この私」を問うことを通じて、存在を問うことになります。 「この私」を問うことは、「この私」に纏わる事象を問うことになります。それは
#当事者 #当事他者 #共同存在 #ハイデガー #当事他者探究 #当事他者論
https://note.com/haveakiller/n/n19c7a5daa470
当事他者探Qその3|非当事者研究
当事他者の存在の前提に当事者がいるように、当事者にも当事他者がついてまわる。当事者と当事他者とは、切っても切れない関係いわば「共同存在」という言い方ができるかもしれません。 「共同存在」は、哲学者ハイデガーの『存在と時間』に由来します。ハイデガーは、「現存在」(とりあえずのところは「人間」の意)はすでにつねに「他者との共同存在」であるとして、次のように書いています。「現存在の存在には、他者たちとの共同存在が不可欠の契機として属している」、さらに「そのつどの事実的な現存在が他人のことなど気にせず、彼らなど要らないと思っていようとも、あるいはいてほしいがいないという場合でも、現存在は
#パルタージュ #partage #部分的つながり #当事者 #当事他者 #当事者研究 #当事他者探究 #当事他者論
https://note.com/haveakiller/n/n357542dd2ef1
当事他者探Qその2|非当事者研究
「部分的」につながるとは、「分かち合う」ことであり、哲学者ジャン=リュック・ナンシーが言うところの「パルタージュ(partage)」です。「パルタージュ」は、『声の分有』(1982)のキーワードとして登場し、「分割=共有」の意味で「分有」と訳されます。 「パルタージュ」の意味について、伊藤潤一郎さんの整理するところでは四つの意味があります。「分割」・「部分」・「共有」に加えて、「出立」の意味もあります。 “partage”は、「出発」を意味する“partir”と同様に、「分ける」を意味するラテン語のpartireを語源としており、「出立」の用法もあります。したがって、「当事者」
#部分的つながり #当事者 #当事他者 #当事者研究 #当事他者探究 #当事他者論
https://note.com/haveakiller/n/n315978e87e0b
当事他者探Qその1|非当事者研究
「当事者(party)」と「当事他者(partner)」との、つながりは「部分(part)的」です。それには消極的理由と積極的理由があります。 消極的な理由として、「部分的」とはまず「全体的」ではありません。「全体的つながり」とは、「当事者」の日常の手助けから資産管理まで何もかも、あるいは空間的にも時間的にも四六時中かかわっているような、つながり方です。 「全体的つながり」において、一つには「当事者」よりも「当事者に関わる人」の都合が優先されやすく、監視ひいては支配になりやすい。たとえば施設介護においては、空間のみならず時間も限られているため、外出のみならず過ごし方までも管理者