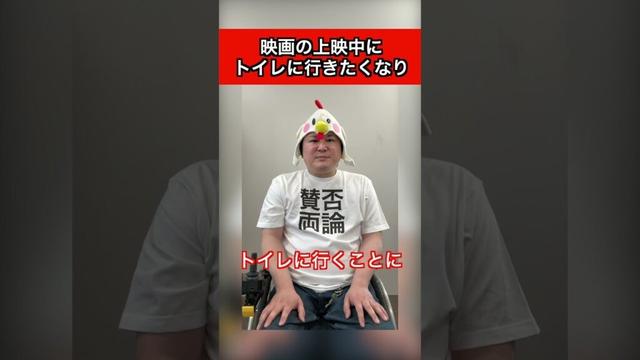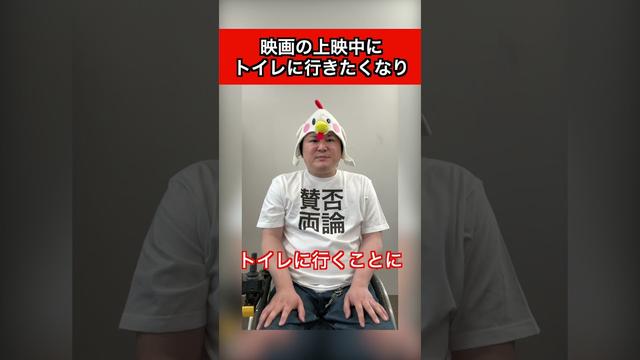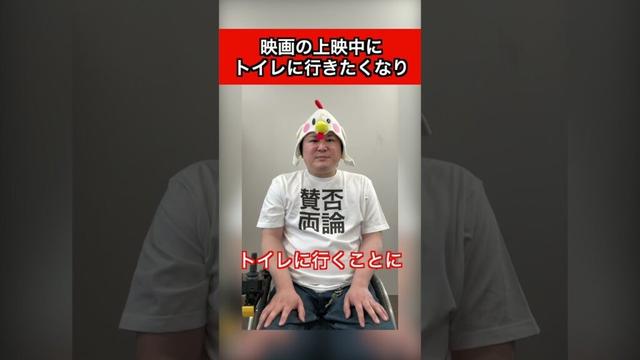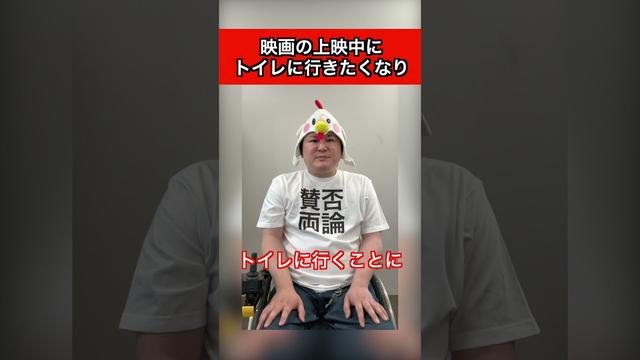ANNテレメンタリー
「技術はあるのに届ける術がないのはなぜ」
かつて「創薬大国」と呼ばれた日本だが…
新薬開発の道のりに「死の谷」が立ち塞がる
https://www.youtube.com/watch?si=pJmL3XVU5simNDI6&v=q_zK2qB2xKs&feature=youtu.be

「技術はあるのに届ける術がないのはなぜ」 かつて「創薬大国」と呼ばれた日本だが…新薬開発の道のりに「死の谷」が立ち塞がる【テレメンタリー】
笑いたいのに笑えない奇病「メビウス症候群」とは?
https://nazology.kusuguru.co.jp/archives/178696

笑いたいのに笑えない奇病「メビウス症候群」とは? - ナゾロジー
人は感情を顔に映す生き物です。 嬉しければ笑い、悲しければ泣く。 そんな当たり前の感情表現ができなくなるとしたら、どうでしょうか? 「笑いたいのに笑顔が作れない」「泣きたいのに顔が動かない」 そうした症状を抱える非常にまれな先天性の神経疾患、それが「メビウス症候群(Moebius syndrome)」です。 メビウス症候群はどのような仕組みで起こるのでしょうか? また治療は可能なのでしょうか? 目次 メビウス症候群はどんな病気?メビウス症候群が起きる「原因」とは何なのか? メビウス症候群はどんな病気? この稀な疾患は、1888年にドイツの神経学者パウル・メビウスによって初めて報告されま…
重度の聴覚障害を持ちながら難病児の親に…「お母さん、仕事するんですか!?」と驚く医師にきっぱり返した“夫の一言” – with class -講談社公式
今回ご紹介するのは、『耳が聞こえなくたって 聴力0の世界で見つけた私らしい生き方』です。著者は生まれつき重度の聴覚障害がある、牧野友香子さん。現在は、ご主人と2人の娘さんと共にアメリカで暮らしています。牧野さんがこれまでの人生で一番大変だったのは、「長女に難病があったこと」だと言います。家族の支えもあり、長女も大きな手術を乗り越え、そろそろ職場復帰を考えたいと思っていた矢先、医師から言われた衝撃的な言葉についてご紹介します。その経験を通し、社会のサポートが整っていないことを痛感したという牧野さん。今につながる出来事とは……? はじめに 私は、生まれた時から耳が聞こえません。補聴器をつけても、人の声はほぼ聞こえません。補聴器を外すと、飛行機の轟音(ごうおん)も聞こえるか、聞こえないかくらい。会話は手話ではなく、「読唇」といって相手の口の動きを読み取って理解し、自分自身の発音でことばを発する「発話」なんです。大阪で生まれ育った私は、ろう学校には行かず、幼稚園、小・中学校は地元の学校に。天王寺高校から、神戸大学に進学し、就職先は第1志望のソニー株式会社へ。趣味の合うファンキーな夫と結婚し、めでたく2人の子どもにも恵まれ……と文字で書くと順風満帆なようですが、聞こえない私の人生、そんな順調にいくわけがありません。一番大変だったのは、長女に難病があったこと。聞こえない中での2歳差の姉妹の育児、仕事をしながらの病院通い。でも、複数回にわたる手術に入院と頑張る長女。そして、どうしても我慢の多くなる、“きょうだい児”の次女のしんどさを思うと、親として弱音を吐いてばかりはいられませんでした。そんな中で長女が2歳、次女が0歳の時に、難聴児を持った親御さんをサポートする「株式会社デフサポ」を立ち上げ、今では子どもたちを連れて家族で渡米。アメリカで生活をしています。いろいろな意味で“規格外”の私ですが、いいこともそうでないことも含めて、おもしろく読んでいただけたらうれしいです。『耳が聞こえなくたって 聴力0の世界で見つけた私らしい生き方』「はじめに」より一部抜粋 「お母さん、仕事辞めますか? 」「僕が専業主夫になります」 長女は常に病院に通うような状態だったのですが、その合間にみんなと同じように定期検診もありました。強く記憶にあるのは、6カ月検診の時。他の赤ちゃんもたくさん区役所に来るんですよね。「みんなの赤ちゃんは健康でいいなあ……」という思いが、どうしてもぬぐえなくて。周りの赤ちゃんは寝返りしたり、健康そうなのに、我が子はいろいろ大変……。それを見るのもつらいし、その事実を突きつけられるのもつらい。また、周りは遠慮して、長女の病気についても聞いてこないですし、かといって自分から言いまくるのも気を遣わせそうだし。「検診になんて行きたくない、人に会いたくない」八方ふさがりのつらさでした。児童館などの人が集まる場所には、一度も行かずに終わりました。 私は育休を取っていたのですが、首の大手術も終え、そろそろ保育園のことや職場復帰を考えたいなと思うタイミングが来ました。当時住んでいたところはまさに保育園の激戦区。生後すぐに保育園を見学して、生まれた年の秋には願書を出さなくてはいけなかったのです。そこで、医師に保育園のための診断書を書いてもらえないかと相談しました。 すると、 「お母さん、仕事するんですか!?」 ……えっ? 「この子は、難病があるから、どういう発達をするかわからないし、家で見てあげないと」 ……ええっ!? 保育園はナシなの⁉ 私、仕事辞めないといけないの!? いろんな思いが頭の中を駆け巡りました。 「えーっと、……そしたら、夫が仕事を辞めます」 と、私の口がつい……。 突然そう言った私に、夫は「ええ! 俺!?」と言いながらも、 「そうですね! 僕が専業主夫になります」 と言い切りました(この時ばかりは、我が夫に改めて惚れ直しました)。すると先生はあわてて、 「え、旦那さんが仕事を辞めるんですか? それは大変ですよね。ちょっと別の方法も考えてみましょう」 と、一気に風向きが変わりました。 紆余(うよ)曲折あったのですが、結果的に子どもを通わせたいと思える保育園が見つかり、そこに行かせていただくことができました。長女と次女と8年間お世話になったのですが、先生方には感謝しかありません。その保育園に通えたことは、本当にいい思い出です。 次のページ 社会のサポートが整っていないことを痛感…
「なぜ私だけ…」50万人に1人の難病の子を出産した聴力ゼロの女性を“絶望から救った”夫の一言 – with class -講談社公式
『耳が聞こえなくたって 聴力0の世界で見つけた私らしい生き方』の著者、牧野友香子さんは生まれつき重度の聴覚障害をもちながら、現在は、ご主人と2人の娘さんと共にアメリカで暮らしています。登録者数12万人超えのYouTube「デフサポちゃんねる」からも伝わる明るさと行動力で、常に前を向いているように見える牧野さんですが、難病をもった長女を出産した直後は“絶望の淵”にいたと言います。今回は本書より、そのときに感じた辛い苦しみや、そこから救いあげた家族の言葉をご紹介します。 はじめに 私は、生まれた時から耳が聞こえません。補聴器をつけても、人の声はほぼ聞こえません。補聴器を外すと、飛行機の轟音(ごうおん)も聞こえるか、聞こえないかくらい。会話は手話ではなく、「読唇」といって相手の口の動きを読み取って理解し、自分自身の発音でことばを発する「発話」なんです。大阪で生まれ育った私は、ろう学校には行かず、幼稚園、小・中学校は地元の学校に。天王寺高校から、神戸大学に進学し、就職先は第1志望のソニー株式会社へ。趣味の合うファンキーな夫と結婚し、めでたく2人の子どもにも恵まれ……と文字で書くと順風満帆なようですが、聞こえない私の人生、そんな順調にいくわけがありません。一番大変だったのは、長女に難病があったこと。聞こえない中での2歳差の姉妹の育児、仕事をしながらの病院通い。でも、複数回にわたる手術に入院と頑張る長女。そして、どうしても我慢の多くなる、“きょうだい児”の次女のしんどさを思うと、親として弱音を吐いてばかりはいられませんでした。そんな中で長女が2歳、次女が0歳の時に、難聴児を持った親御さんをサポートする「株式会社デフサポ」を立ち上げ、今では子どもたちを連れて家族で渡米。アメリカで生活をしています。いろいろな意味で“規格外”の私ですが、いいこともそうでないことも含めて、おもしろく読んでいただけたらうれしいです。『耳が聞こえなくたって 聴力0の世界で見つけた私らしい生き方』「はじめに」より一部抜粋 「育てられないかも」と言った私を支えたことば 長女を産んですぐ見た目でもわかったし、看護師さんとドクターがバタバタした雰囲気で、ちょっと抱っこしたらすぐに別室に連れていかれたので、「あ、この子病気あるな」と感じたんです。ただ、珍しい病気なので、具体的にどんな病気なのかがなかなかわからなくて。複数の診療科に行って、いろんな診察を受けるための書類に大量にサインをした覚えがあります。入院中なんて、ずーっと携帯で朝から夜中まで「骨が短い」「低身長」「難病」といろんなことばで検索したりして、げっそりして。正直、出産の喜びなんてなくて、「なんでうちの子なんだろう……」って毎日泣き崩れていました。育てられるのかな、どんな病気なんだろうか、私たちも子どもの未来もどうなるんだろう……というのがずっと頭にありました。子どもはNICU(新生児集中治療室)に入院していて、私は先に退院し、ボロボロのメンタルでバスと電車を乗り継いで病院まで母乳を届けに行っていたんですよね。ドーナツクッションを持ってバスに乗って、お股も痛いし、体もしんどいし、精神的にも肉体的にもこんなにつらいことって、これまでもこの先もない気がします。皆が子どものかわいい写真とかをSNSに上げているのを見て、「なんで私ばっかりこんな苦労があるの! 私にはこの子を育てられない、育てたくない!」とさえ思いました。本当はそんなこと思っちゃいけないって、理性ではわかっているんです。でも、心から受け入れられる未来が来るなんて思えなかった。 私自身、耳が聞こえなくても、努力したり工夫したりしながら前向きに楽しく過ごせていたのに、どうして私にばっかりこんな試練があるんだろう……。周りの人たちは耳も聞こえて、苦労もせずに健康な子どもを産んでいて幸せそう。楽しく子どもを育てる、そんな当たり前の幸せすら、自分のもとにはやって来ないのか……。そして、「我が子を育てたくない」って思うなんて、私は人としてありえないのかも……。人として、母としてだめな人間なんだ……と、絶望の淵にいました。 次のページ そんなわたしを救ってくれたのは…
「耳が聞こえない」を言い訳にしない――重度の聴覚障害を持つ女性が、幼少期に親から言われていたこと – with class -講談社公式
今回ご紹介するのは、『耳が聞こえなくたって 聴力0の世界で見つけた私らしい生き方』です。著者は生まれつき重度の聴覚障害がある、牧野友香子さん。現在は、ご主人と2人の娘さんと共にアメリカで暮らしています。登録者数12万人超えのYouTube「デフサポちゃんねる」でも垣間見える、牧野さんのパワフルで笑顔溢れる前向きマインドはいったいどこからきているのか、今回は本書より、牧野さんの幼少期のエピソードをお届けします。 はじめに 私は、生まれた時から耳が聞こえません。補聴器をつけても、人の声はほぼ聞こえません。補聴器を外すと、飛行機の轟音(ごうおん)も聞こえるか、聞こえないかくらい。会話は手話ではなく、「読唇」といって相手の口の動きを読み取って理解し、自分自身の発音でことばを発する「発話」なんです。大阪で生まれ育った私は、ろう学校には行かず、幼稚園、小・中学校は地元の学校に。天王寺高校から、神戸大学に進学し、就職先は第1志望のソニー株式会社へ。趣味の合うファンキーな夫と結婚し、めでたく2人の子どもにも恵まれ……と文字で書くと順風満帆なようですが、聞こえない私の人生、そんな順調にいくわけがありません。一番大変だったのは、長女に難病があったこと。聞こえない中での2歳差の姉妹の育児、仕事をしながらの病院通い。でも、複数回にわたる手術に入院と頑張る長女。そして、どうしても我慢の多くなる、“きょうだい児”の次女のしんどさを思うと、親として弱音を吐いてばかりはいられませんでした。そんな中で長女が2歳、次女が0歳の時に、難聴児を持った親御さんをサポートする「株式会社デフサポ」を立ち上げ、今では子どもたちを連れて家族で渡米。アメリカで生活をしています。いろいろな意味で“規格外”の私ですが、いいこともそうでないことも含めて、おもしろく読んでいただけたらうれしいです。『耳が聞こえなくたって 聴力0の世界で見つけた私らしい生き方』「はじめに」より一部抜粋 家では「聞こえないからできない」は許されない 小さいころから両親に言われていたのは、聞こえを言い訳にはしないということ。もちろん、聞こえなくてできないことはやる必要はないけれど、そうじゃないことは基本的に「当たり前にやる!」環境でした。 「聞こえないからできなくてもいい」 「聞こえないからあきらめてもいい」 なんてことが、我が家ではまったくなかったんです。音楽の授業でリコーダーを吹くことがあった時も、聞こえなくても吹くことはできるし、ピアノだって、聞こえなくても弾くことはできるでしょ? っていう感じで。リコーダーの宿題をやりたくなかった私が、聞こえないし難しいって! と聞こえないことを理由にサボろうとすると、「『ド』の鍵盤(けんばん)を押せば『ド』の音が出るのと同じで、リコーダーも『ド』の指をすれば『ド』が出るやろ」と言われて、ぐうの音も出ませんでした。バイオリンは、自分の弾いた音を聞いて判断するからできなくても仕方がない。でも、ピアノや木琴は聞こえなくても関係ない。「だって叩いたら、その音が出るねんから」って。いや、そりゃそうだけど……。笑リコーダーは吹けて当然、ピアノも木琴もできて当然、楽譜だって読めて当然。だって、楽譜を読むのに聞こえないことは関係ないから。聞こえないからこそ、聞こえに甘えずやることはちゃんとやる! というのが、両親の考えでした。「聞こえないから勉強したくない」とか「聞こえないから宿題できない」なんてことがまかり通る家じゃないから、私も「そういうもんかな」と納得していました。今になって思うと、両親の考え方が私を形成したと思います。自分にできないことがあっても、「聞こえないからしょうがない」とあきらめる前に、「どうやれば、聞こえなくてもできるようになるんやろ?」と考えるようになったから。「聞こえないからできない」がない分、「聞こえないからやっちゃダメ」もあまりなくて、やりたいことは自由にさせてもらいました。スイミングを習っていた時、水の中では補聴器を外すので、泳いでいる時はまったくの無音。コーチが何か言っていても全然聞こえなくて、口パクで読める時はよかったけど、毎回配慮してもらえるわけでもなく。それはそれで大変だったのですが、泳ぐのも、スイミングの後みんなでタコせんを食べるのも、楽しかった。聞こえないことに甘えず、いろんなことに挑戦するのが当たり前でした。 次のページ とてもかわいがってくれた祖母は…
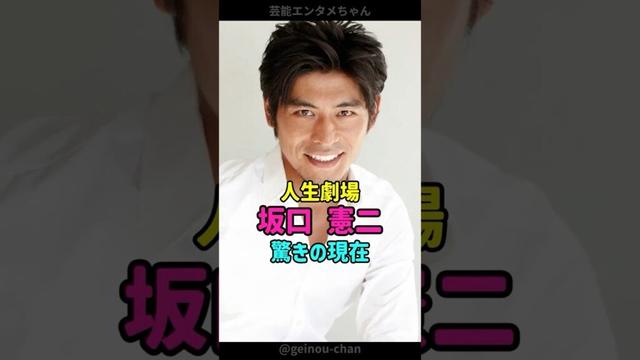
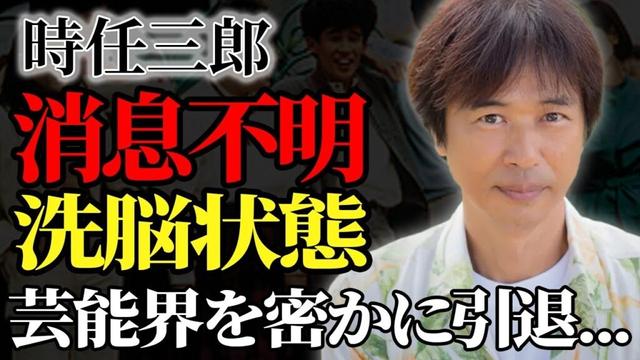

 ナゾロジー
ナゾロジー