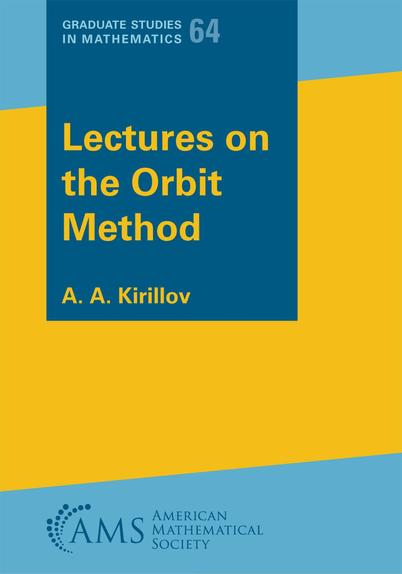#Calculus #LieAlgebra #LieAlgebra #QuantumAlgebra #ClusterAlgebra
丸を線で結んだ図形(の一般化)の線を矢線に変えた図形を箙(中事案啓さんによるquiverの翻訳、えびらと読む)と呼びます。エビラについては添付画像も参照(笑)。
箙に対しては、矢線の向きの情報も利用でき、さらに様々な基本的な数学的対象を定義することができます。
例えば、クラスター代数とその変種達(量子化への拡張やフリーズパターンへの特殊化)は箙情報を与えるごとに定義されます。
クラスター代数の特殊化であるフリーズパターンに関する詳しい解説(高校生に配ったもの)が次のリンク先にあります。
https://genkuroki.github.io/documents/20120810FriezePattern.pdf
#Calculus #LinearAlgebra #LieAlgebra #QuantumAlgebra
一般化された図形の例は添付画像。添付画像は
https://mathtod.online/@genkuroki/204074
より。この手の図形に対してLie代数を対応させる方法を天下り的に説明するのは易しいです。難しいのはそんなことをして何がうれしいかの説明。
添付画像は対応するLie代数が有限次元になる場合です。図形が複雑になると対応するLie代数は通常無限次元になり、制御が非常に難しくなる。
図形をそのまま扱うのは大変なので、通常、図形の情報を(対称化可能)一般Cartan行列 $A=[a_{ij}]$ に翻訳して扱います。$A_n$ 型の図形に対応する(一般)Cartan行列は本質的に離散線分状の離散Laplacianになります。$A_n$ 型の図形に対応するLie代数はトレースが0の行列全体で構成される $\mathrm{sl}(n+1)$ になります。
genkuroki on mathtod.online
https://mathtod.online/@7shi/203900 四元数と3次元の回転の関係は「Lie群 $SU(2)$ の随伴表現」。 $i,j,k$ を正規直交基底とする3次元Euclid空間に $i,j,k$ 軸を中心とする角度 $2\theta$ の回転がそれぞれ\begin{align*} &a\mapsto e^{i\theta}a e^{-i\theta},\\ &a\mapsto e^{j\theta}a e^{-j\theta},\\ &a\mapsto e^{k\theta}a e^{ -k\theta} \end{align*}で作用している。 Lie群 $SU(2)$ の四元数体 $\mathbb H$ を使った実現の仕方は\[ SU(2)=\{\,g\in\mathbb H\mid |g|=1\,\}. \]これのLie代数が\[ \operatorname{su}(2)=\mathbb Ri+\mathbb Rj+\mathbb Rk. \]$SU(2)$ の $\operatorname{su}(2)$ への随伴表現の特殊化が上で示した式。
#Calculus #LinearAlgebra #LieAlgebra
o-o-o-o-o
のように丸を線で結んだ図形を「グラフ」と呼ぶことがあります。ここでは例として横一直線の単純なものを例に挙げましたが、枝分かれしていたり、閉路があったりしてもよい。そういう丸を線で結んだ図形の上ではランダムウォークを考えることができる。それは離散的なラプラシアンを丸を線で結んだ図形の上で考えることと実質的に同じです。
そしてここからが相当に非自明な話になってしまうのですが、丸を線で結んだ図形に丸Aと丸A自身を結ぶ線(長さ1のループ)が存在しなければ(以下簡単のためこの条件を仮定)、その図形に対して、Kac-Moody代数と呼ばれるLie代数やそのq差文化である量子展開環が定義されます。丸を線で結んだ図形に表現論的に基本的なKac-Moody代数や量子展開環の定義情報がすべて詰まっている!
実際には丸を線で結んだ図形はさらに一般化され、一般化された図形に対して、Kac-Moody代数と量子展開環が定義されます。
続く
#Calculus #LinearAlgebra #LieAlgebra
$n$ 次元列ベクトル $v=[v_k]$ を
$$
v_k = f(x_k), \ x_k=kh, \\ f(x_0) = f(x_{n+1}) = 0
$$とおくと、$A_n$ 型Cartan行列 $A_n$ について、$Av$ の第 $k$ 成分は
$$
2f(x_k) - f(x_k-h)-f(x_k+h)\\ =
-h^2 f''(x_k) + O(h^3)
$$と書けるので、$A_n$ は
境界条件 $f(x_0)=f(x_{n+1})=0$ のもとでの離散Laplacian
です。Laplacianの固有値、固有函数を求める問題は基本的に重要なので、$A_n$ 型のCartan行列 $A_n$ の固有値、固有ベクトルを求める問題も基本的に重要だということになります。
周期境界条件に対応する離散Laplacianの行列表現には
$A^{(1)}_n$ 型のaffine型一般Cartan行列
という名前が付いています。
$$
B_n = \left( \begin{array}{ccccccc} 0&1&0&0&\ldots&0&0\\ 1&0&1&0&\ldots&0&0\\ 0&1&0&1&\ldots&0&0\\ 0&0&1&0&\ldots&0&0\\ \vdots&\vdots&\vdots&\vdots&\ddots&\vdots&\vdots\\ 0&0&0&0&\ldots&0&1\\ 0&0&0&0&\ldots&1&0 \end{array} \right)
$$に対する$$
A_n = 2E_n - B_n
$$($E_n$ は単位行列)には
$A_n$ 型Cartan行列
という名前がついています。$BCDEF$ 型もある。
$\mathbb R^{n+1}$ の標準基底を $e_i$ と書くとき、
$$
h_i = e_i - e_{i+1}
$$達の内積表が $A_n$ 型Cartan行列に一致する。
Cartan行列が出て来る数学はおもろいです。
$sl(n)$, $so(n)$, $sp(2n)$ のroot basisの行列実現の公式表はLie代数について勉強し始めるときに、最初にやるべき作業。
$sl(n)$ の場合には、
$$
H_i = E_{ii}-E_{i+1,i_1}, \\
E_{kl} \quad (k\ne jl)
$$がCartan部分代数のcoroot basisおよびroot basisです。 $E_{ij}$ は行列単位($(i,j)$ 成分だけ1で他が0の正方行列)。
Cartan行列がきちんと出て来るところまでは公式表を作っておきたい。
複素古典型Lie代数(実型はひとまず無視)の行列による実現をどう取るかはそれなりに悩む価値がある問題。公式集を作っておくと例で確認したいときに便利。
私は大学4年~M1くらいのときには $\mathbb C^n$ の非退化対称双線型性形式として$$
[(e_i, e_j)] =
\begin{bmatrix}
& & & 1 \\
& & 1 & \\
& \text{/} & & \\
1 & & & \\
\end{bmatrix}
$$を採用して $so(n)$ を定義していました。
このようにすることの利点はCartan部分代数 $\mathfrak h$ を対角行列部分と一致させ、上下の極大べき零部分代数を上下三角行列部分に一致させることができるから。
Jimbo-Miwaのソリトン方程式関係の論文で採用している実現はこれに近かった。
$sp(2n)$ についても同様にできる。
https://mathtod.online/@sr_ambivalence/825850
角運動量演算子達 $J_{x,y,z}$ とそれらと可換な $J$ の関係は、$SO(3)$ もしくは同じことなのですが $SU(2)$ のLie環の話に一般化されています。
実際には複素化して $SL_2(\mathbb C)$ のLie環として扱うことが多いです。複素化は昇降演算子を定義するために必要。
$J$ に対応するLie環論における対象は Casimir element とか Casimir operator と呼ばれています。
$SL_2$ の $2$ を $n$ に一般化すると、Casimir演算子は $n-1$ 個に増えます。
$SL$ を $GL$ にすると $n$ 個になり、Casimir elements が基本対称式の量子化になっていることが明瞭になります。
2次のCasimir elementのアフィン化がVirasoro代数の菅原構成。
3次以上のCasimir elementsはアフィン化は複雑な手続きを経てW代数を生成。