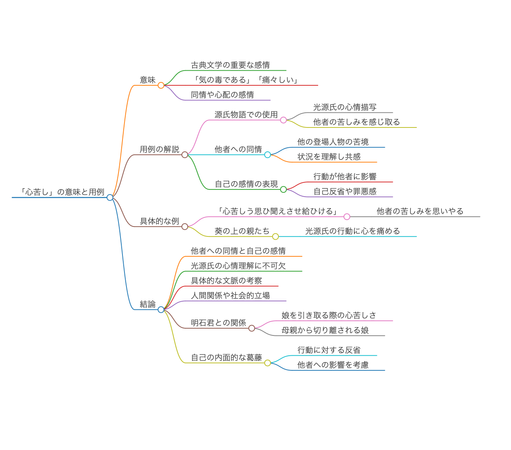著者は論理的思考を四つの分野(論理学・レトリック・科学・哲学)にわけている(特に表序‐1「四分野の思考法の比較」4‐5)。
レトリックは「説得の技術」(18)で、「説得するとは、受け手の心からの同意を引き出し、言論によって受け手の考えや行動を変えること」(19)とこの分野に「受け手」(送り手の相手)を持ち出す。
著者は科学的探究に即してアブダクションを取り上げて、「常識的な期待に背くような驚くべき事実の観察から起こる」(29)と始める。「驚くべき」とは常識として無視ないし黙殺していたからこそなのだから、常識を変更して改めて共有するためにレトリックが必要になる(常識に従うだけなら常識外へ出られない)。
つまりレトリックとして把握する分野ではかかわる者相互の理解が共有されていない、と考える必要がある。
つまり四つの分野(他に領域などの言回しを考えることができる)は完全に横並びというより、共有が到底自明でないという意味で、レトリックは他に先立って働かねばならない、と考えることができる。
横並びでない点をつめきれていない印象。